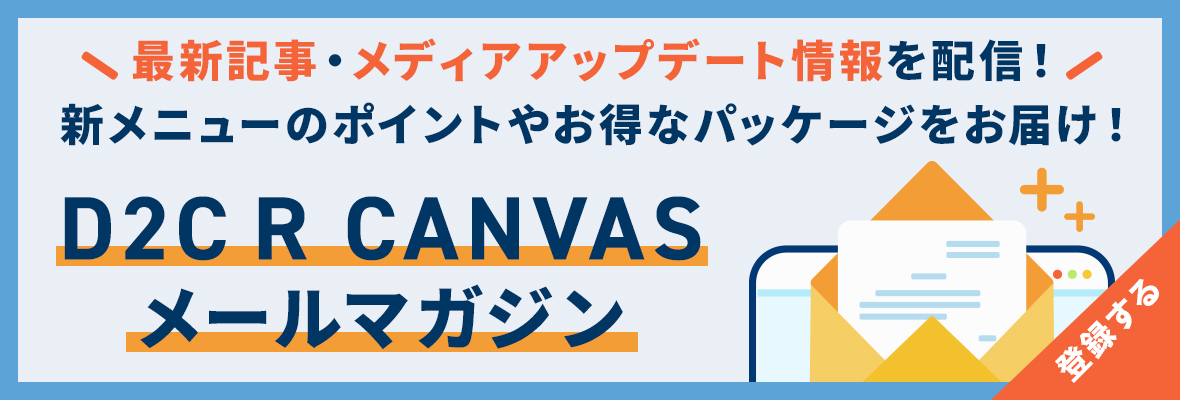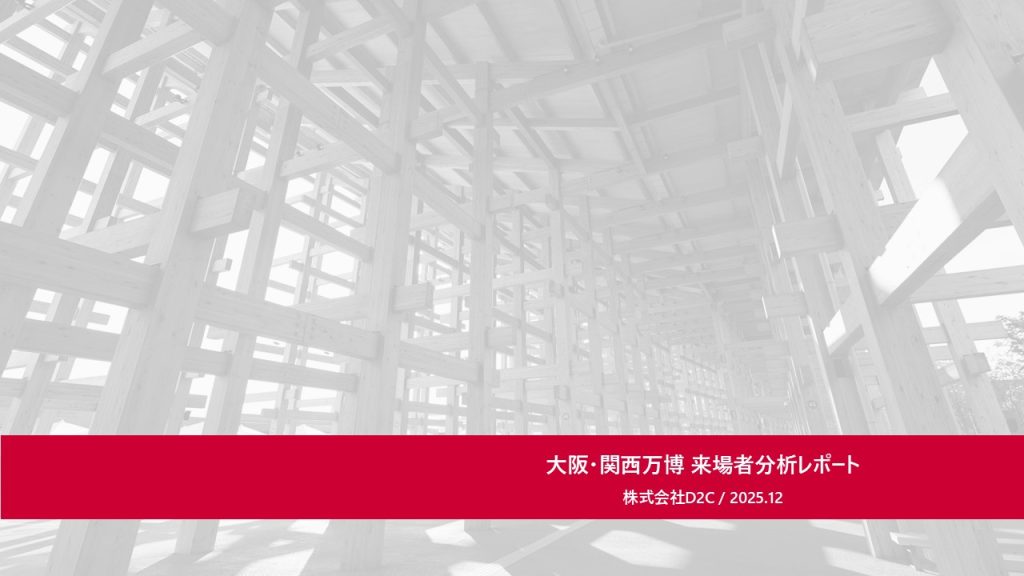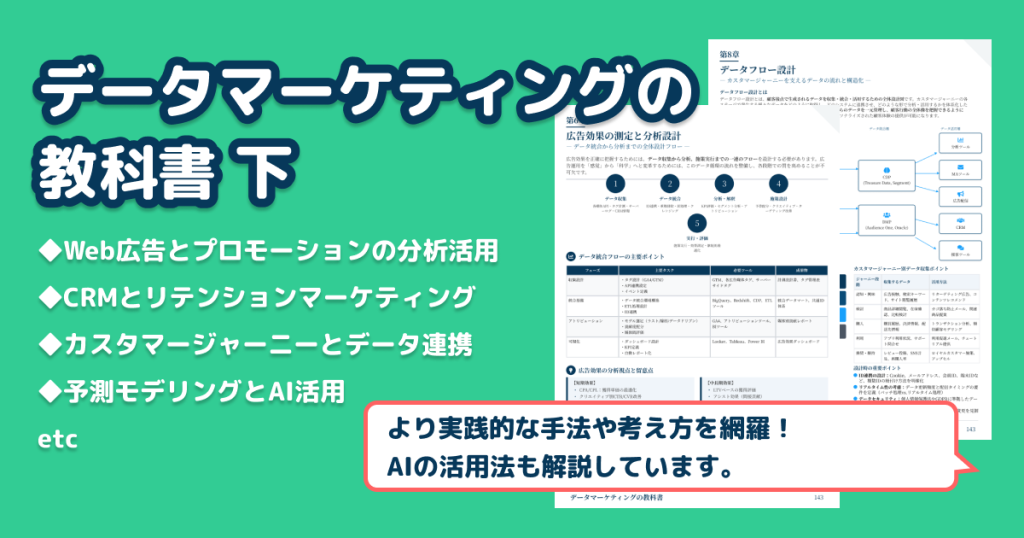競合分析のやり方・手順とは?フレームワークとツール、分析の注意点まで紹介

みなさん、こんにちは。
ビジネス環境が日々変化する中で、自社の立ち位置を正確に把握し、競争優位性を作ることはますます重要になっています。そこで必要となるのが「競合分析」です。
今回は、競合分析の基本的な進め方から、実践で役立つフレームワーク、分析を効率化するツール、すぐに使えるテンプレートまでをわかりやすく解説します。競合を知ることで、自社の強みや差別化ポイントが明確になり、より精度の高いマーケティング戦略や事業計画の立案が可能になります。
これから競合分析に取り組みたい方や、より効果的な分析方法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
競合分析とは?
競合分析とは、自社と同じ市場で活動する他社(=競合)について調査・分析を行い、自社の立ち位置や今後の戦略に活かすためのマーケティング手法です。競合企業の製品・サービス、価格、販促方法、WebサイトやSNSの動向などを幅広く把握することで、自社の強みや弱みを客観的に理解できるようになります。
特に、商品開発やマーケティング戦略の策定、営業活動の方向性を見直す上で、競合分析は欠かせないプロセスとなっています。自社視点だけでは見えにくい市場全体の動向や顧客ニーズを、競合という他者の鏡を通して把握することができるからです。
競合分析と市場分析・自社分析の違い
「競合分析」と混同されやすい言葉に、「市場分析」や「自社分析」があります。いずれもマーケティング戦略の立案に欠かせない要素ですが、それぞれの視点には違いがあります。
| 分析の種類 | 主な分析対象 | 視点 |
|---|---|---|
| 市場分析 | 業界全体・トレンド・顧客ニーズ | マクロ視点(環境・顧客) |
| 競合分析 | 競合他社 | 他社視点 |
| 自社分析 | 自社の強み・弱み・資源 | 自社視点 |
競合分析は、「同じ市場内で顧客を取り合う相手(競合)」を中心に据えた分析です。一方で、市場分析はより広い視野で業界全体の構造やトレンドを捉え、自社分析は内部資源や課題にフォーカスします。
これら3つの分析をバランスよく組み合わせることで、自社の強みを最大限に活かしたマーケティング戦略を構築できるようになります。
▼競合他社の種類についての記事はこちら
なぜ競合分析が必要なのか?
競合分析が必要とされる主な理由は、「自社の戦略に客観性と説得力を持たせるため」です。市場環境は常に変化しており、顧客のニーズも日々進化しています。そんな中で、他社の動向を無視した独自路線だけでは、的外れな戦略になってしまう可能性があります。
競合分析を行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- ビジネス戦略の立案に役立つ
- マーケティング戦略の改善につながる
- 商品・サービスの差別化ポイントを明確にできる
たとえば、競合が価格訴求型のキャンペーンを展開している中で、自社が機能重視の訴求を行っても成果が出ないケースがあります。このようなギャップにいち早く気づけるのも、競合分析の利点です。
競合分析の目的と得られる効果
競合分析は、単なる情報収集ではなく、ビジネスの方向性を見極めるための「戦略的な意思決定」に直結する重要な取り組みです。競合他社の強み・弱み、自社との違い、顧客が求めている価値などを把握することで、自社が進むべき道を明確に描くことができます。
ビジネス戦略の立案に役立つ
競合分析は、経営全体の方針や事業戦略を考える上で強力な指針となります。
たとえば、業界内で急成長している企業がどのようなビジネスモデルを採用しているのかを分析すれば、自社が今後注力すべき領域やサービス設計の方向性が見えてきます。また、競合の失敗事例からは、リスク要因や市場の落とし穴を事前に察知することも可能です。
このように、競合の動向を俯瞰することで、「何に投資すべきか」「どこで差をつけるか」という経営判断の精度が向上します。
マーケティング戦略の改善につながる
競合分析は、広告やプロモーション、SEO、SNS運用などのマーケティング活動にも大きな効果をもたらします。
競合の打ち出しているメッセージやプロモーション施策、使用している媒体などを観察することで、ターゲット層に響く訴求軸や、今どのチャネルが成果を出しやすいのかを把握できます。
また、競合よりも検索順位が低いキーワードや、獲得できていない流入経路を見つけることで、自社のマーケティング施策に新たな打ち手を追加するヒントが得られます。
商品・サービスの差別化ポイントを明確にできる
競合分析を通じて得られる最大の価値のひとつが、「自社ならではの価値=差別化ポイント」の発見です。
同じような商品・サービスが並ぶ中で、顧客がどの企業を選ぶかは、ほんの小さな違いや印象によって左右されます。そのためには、競合が提供していない価値、自社だけが実現できる強みを明確にする必要があります。
競合の商品構成、価格設定、導入事例、カスタマーサポート内容などを細かくチェックすることで、「他社にはないが自社にはある」価値が浮き彫りになり、魅力的な差別化戦略を築くことができます。
競合分析の主な種類
競合分析と一口に言っても、目的や状況に応じてさまざまなアプローチがあります。中でも代表的な手法には、「直接競合・間接競合の分類」から、代表的なフレームワークが7つほどあり、それぞれ異なる視点から市場や競合を把握できます。
ここでは、競合分析においてよく使われる代表的な種類と、それぞれの特徴・活用シーンについてご紹介します。
直接競合と間接競合の違い
競合を分析する際、まず押さえておきたいのが「直接競合」と「間接競合」の違いです。
- 直接競合:自社と同じ商品・サービスを提供しており、同じ顧客層をターゲットにしている企業
(例:A社のオンライン英会話 vs B社のオンライン英会話) - 間接競合:異なる商品・サービスでありながら、顧客のニーズを部分的に満たす競合
(例:オンライン英会話 vs 英会話スクール、英語学習アプリ)
競合分析では、直接競合だけでなく、顧客の選択肢として浮上しうる間接競合にも目を向けることが重要です。見落としがちな間接競合こそ、自社のポジションに影響を与えることもあります。
▼競合の種類はこちらの記事で詳しく解説
ファイブフォース分析
ファイブフォース分析(Five Forces Analysis)は、業界内の競争環境を5つの力で分析する手法です。特定の市場における競争の激しさや、収益性の構造を理解するために活用され、たとえば新たな業界に参入しようとする際に、既存の競合の強さや、サプライヤー・顧客の影響力の大きさを事前に評価するのに役立ちます。
- 業界内の競合他社(既存の競争)
- 新規参入者の脅威
- 代替品の脅威
- 売り手の交渉力
- 買い手の交渉力
PEST分析
PEST分析は、競合環境をマクロな視点で捉えるための手法で、4要素から外部環境を分析します。自社と競合を取り巻く外的要因を洗い出すことで、業界全体に影響を及ぼすトレンドや規制、技術革新の兆しを把握でき、たとえば新しい法律が施行された際に、どの競合が影響を受けやすいかを比較するなど、市場機会とリスクを同時に捉えるのに有効です。
- 政治(Politics)
- 経済(Economy)
- 社会(Society)
- 技術(Technology)
▼PEST分析について詳しくはこちら
3C分析
3C分析は、3つのCの視点から市場環境を分析するフレームワークです。自社の成功要因(KSF)を見出すフレームワークです。たとえば競合がどのターゲット層にアプローチしているのか、自社の提供価値が市場のニーズにどれほどマッチしているのかを明確にすることで、差別化やポジショニング戦略の方向性が定まります。競合分析の中では特にマーケティング戦略の立案時に有効です。
- Customer(市場・顧客)
- Company(自社)
- Competitor(競合)
▼3C分析について詳しくはこちら
SWOT分析
SWOT分析は、4つの要素を整理することで、自社と競合の戦略環境を俯瞰するフレームワークです。競合に対して自社の強みがどの機会と結びつくか、あるいは競合の脅威に対してどの弱点がリスクになるかといった関連性を読み解くことで、競合に対する攻守のバランスを戦略的に考えることができます。
- Strength(強み)
- Weakness(弱み)
- Opportunity(機会)
- Threat(脅威)
▼SWOT分析について詳しくはこちら
STP分析
STP分析は、3ステップで競合の市場戦略を分析し、自社の優位性を明確にするフレームワークです。競合がどのセグメントをターゲットにしているかを把握した上で、あえて別のニーズ層を狙うことでブルーオーシャンを見つけたり、自社のポジションを差別化して競合との重複を避けたりするのに有効です。
- Segmentation(市場の細分化)
- Targeting(標的市場の決定)
- Positioning(差別化と訴求点の明確化)
▼STP分析について詳しくはこちら
4P分析
4P分析はマーケティング・ミックスの4要素に着目し、競合のマーケティング戦略を多角的に分析するフレームワークです。競合がどの製品ラインナップを提供し、どの価格帯で、どの販売チャネルを活用し、どのようなプロモーションを展開しているかを調査することで、自社との違いを可視化し、独自の打ち手を考えるベースになります。
- Product(製品)
- Price(価格)
- Place(流通)
- Promotion(販促)
▼4P分析について詳しくはこちら
4C分析
4C分析は4つの視点から競合と自社を比較します。競合がどのように顧客のニーズを満たし、どのようなコスト感や利便性を提供しているか、またどのような接点(広告・SNS・接客など)で関係を築いているかを分析することで、より生活者目線に立った競合理解が可能になります。
- Customer Value(顧客価値)
- Cost(顧客負担)
- Convenience(利便性)
- Communication(コミュニケーション)
▼4C分析について詳しくはこちら
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、競合企業が製品やサービスを生み出す過程を「価値の連鎖」として捉え、各活動(購買物流・製造・出荷物流・マーケティング販売・サービスなど)の中でどこに強みや差別化があるかを分析する手法です。たとえば競合が製造に強みを持つのか、それとも販売・顧客サポートに力を入れているのかを見極め、自社が対抗・模倣すべきポイントや、新たに差をつけられる領域を探るのに役立ちます。
- 購買物流
- 製造
- 出荷物流
- マーケティング販売
- サービス
VRIO分析
VRIO分析は、4つの観点から自社や競合の経営資源が競争優位につながるかを評価する手法です。競合が持っている特定の技術や人材、ブランド力が、どの程度持続的競争優位につながっているのかを判断でき、たとえば競合が模倣困難な資産を持っている場合には、自社がそれにどう対抗するかという視点が戦略策定のカギになります。
- Value(価値)
- Rarity(希少性)
- Imitability(模倣困難性)
- Organization(組織体制)
競合分析の手順・進め方
競合分析は、ただ情報を集めて終わるものではなく、「目的を持って、戦略に活かす」ことが重要です。計画的に進めることで、自社にとって本当に意味のある分析結果を得ることができます。
ここでは、競合分析を実際に行う際の基本的な4つのステップをご紹介します。初めて分析を行う方でも実践しやすい流れになっているので、ぜひ参考にしてみてください。
①競合を洗い出す
最初のステップは、自社と競合する企業をリストアップすることです。競合には「直接競合(同じ商品・顧客層)」「間接競合(別の方法で同じニーズを満たす)」の両方が存在するため、視野を広げて検討しましょう。
競合の洗い出しに役立つ視点
- 同じ検索キーワードで上位表示されているWebサイト
- 顧客が他社と比較検討している企業
- 類似ジャンルでSNSや広告に露出している企業
②情報を収集する
競合が特定できたら、次はその企業に関する情報を収集していきます。対象は以下のような多岐にわたります。
- Webサイト(構成・LP・導線・デザイン)
- 商品・サービスのラインナップ、価格、特徴
- SNS運用状況(投稿頻度、反応、フォロワー数など)
- 広告出稿状況(検索広告、ディスプレイ広告、SNS広告など)
- 口コミやレビュー、顧客の声
- IR資料(上場企業であれば)
また、ツールを活用することで効率的に情報を収集することも可能です。記事の後半で役立つツールをご紹介しております。
③分析フレームワークに当てはめる
収集した情報を、整理・分析する段階です。このとき活用するのが、SWOT分析や3C分析、ポジショニングマップなどのフレームワークです。
たとえば:
- SWOT分析 → 競合の強み・弱みから、自社が取るべき戦略を探る
- 3C分析 → 顧客・競合・自社の関係を可視化し、機会や差別化ポイントを見つける
- ポジショニングマップ → 市場内の立ち位置を視覚的に整理する
このプロセスにより、バラバラだった情報が「戦略につながるヒント」として見えてきます。
④結果から戦略を導く
最後のステップは、分析結果をもとに自社の戦略を立案することです。以下のような問いを考えながら、具体的な施策につなげていきましょう。
- 競合にない自社の強みは何か?
- 顧客が未充足なニーズはどこか?
- 価格・品質・サポートなどで、どこを軸に戦うか?
- 競合の戦略から学ぶべき点や避けるべき落とし穴は?
戦略に落とし込む際は、マーケティング施策、商品開発、広告戦略、営業資料など、実務に紐づくアクションプランとして整理するのが理想です。
競合分析で活用できる情報源・データ
競合分析を成功させる鍵は、「どこから」「どのような」情報を収集するかにあります。現代のビジネス環境では、企業のWebサイトやSNS、公開資料に加え、専門ツールや顧客の声など、あらゆる場所に競合分析のヒントが存在します。
ここでは、実務で役立つ代表的な情報源と、それぞれから得られるデータ・示唆について紹介します。
WebサイトやIR資料
競合企業の公式Webサイトは、最も基本的かつ信頼性の高い情報源です。以下のような情報を収集できます:
- サービス・製品の内容、料金プラン、導線設計
- 強調している機能や打ち出し方(コピーやCTA)
- 導入事例、FAQ、ブログやホワイトペーパー
- 採用情報(成長戦略や組織の方向性を読み取れる)
また、上場企業であれば、IR資料(決算説明資料・中期経営計画など)も競合分析に有効です。企業の戦略、売上構成、注力領域などを把握できます。
SNSや口コミサイト
近年では、SNSやレビューサイトが競合分析の“リアルな声”を知るための重要な情報源となっています。
- TwitterやInstagram、YouTubeでの投稿内容・トーン
- フォロワー数やエンゲージメント率(いいね・リポスト)
- 口コミサイト(Googleレビュー、価格.com、食べログなど)の評価内容
- ユーザーの不満・称賛ポイントの傾向
これらの情報は、顧客がどこに価値を感じ、何に不満を持っているかを把握するのに最適です。定性情報も重視することで、より顧客目線に立った分析が可能になります。
SEO・広告の競合ツール
Web上の競合状況を定量的に把握したい場合は、SEO・広告関連の競合調査ツールが非常に有効です。以下のようなツールが代表的です。
- Keywordmap:SEOキーワード、競合ドメイン、流入経路分析
- SimilarWeb:トラフィック構成やユーザー属性
- Ahrefs:競合の自然検索・広告出稿キーワード
これらを活用することで、競合の検索対策・集客チャネル・広告戦略を数値ベースで把握できます。
顧客アンケート・インタビュー
競合分析の中でも、最も実践的で信頼性が高いのが“顧客の声“です。
- 競合と比較して、なぜ自社を選んだのか
- 競合の商品・サービスの印象や不満点
- 検討段階でどの企業と比較したか
- 購入・導入の決め手
こうした情報は、アンケートやインタビュー、営業時のヒアリングから得ることができます。既存顧客だけでなく、見込み客や失注顧客の声も貴重です。
競合分析に役立つツール
競合分析を効率的かつ正確に進めるためには、専用のツールを活用することが不可欠です。近年では、SEO・広告・トラフィック分析など、さまざまな目的に対応したツールが登場しており、それらを使いこなすことで定量的かつ網羅的な競合調査が可能になります。
ここでは、特に実務で活用されている代表的な競合分析ツールをご紹介します。
docomo data square
docomo data squareは、NTTドコモが保有するデータを活用した顧客分析基盤です。自社の商材やサービスだけでなく、競合他社の購買履歴や利用ログから分析を行うことで顧客を可視化することが可能です。
- 自社商材を活用するユーザーの動向
- 既存顧客の日常行動
- 他社の商材を購買しているユーザー動向
- アプローチしやすいチャネル
オンライン上の分析だけでなく、位置情報を活用したオフラインでのデータ分析が可能ですので、オンオフ統合で自社/競合分析を行いたい時に活用することができます。
\ D2C Rの専門データアナリストが解析 /
Keywordmap

Keywordmap(キーワードマップ)は、SEO・コンテンツマーケティングの領域で人気のある国産の分析ツールです。競合分析においては以下のような機能が活用できます。
- 競合ドメインの自然検索キーワードの抽出
- 共起語や検索意図の把握によるコンテンツ設計
- 上位表示されている記事構造の分析
- 広告出稿キーワードの調査
特に日本語に最適化されている点が強みで、国内市場に特化したSEO分析や競合サイトの可視化に向いています。
SimilarWeb
SimilarWeb(シミラーウェブ)は、Webサイトのトラフィック分析に特化したグローバルツールです。競合サイトの以下のような情報を調査できます。
- 月間訪問数、滞在時間、直帰率などのアクセス指標
- 主要な流入チャネル(検索、SNS、リファラルなど)
- 人気ページ・検索キーワード
- ユーザー属性(地域、デバイスなど)
自社サイトでは取得できない、他社サイトのトラフィックデータを比較・分析できる点が最大の魅力です。市場シェアや競合の集客戦略を定量的に把握するのに役立ちます。
Ahrefs
Ahrefs(エイチレフス)は、SEOおよび検索広告の競合分析において世界的に利用されているツールです。主な活用ポイントは以下の通りです。
- 競合サイトの被リンク(バックリンク)分析
- 自然検索キーワードと順位の確認
- 広告出稿キーワードや広告文のチェック
- トラフィック推移や競合比較レポートの出力
SEOのテクニカルな視点から競合を徹底的に調べたい場合や、グローバルな競合を対象とする場合に特に有効です。
Googleアナリティクス / サーチコンソール
Googleが無料で提供するGoogleアナリティクス(GA)とGoogleサーチコンソールは、直接的な「競合分析ツール」ではないものの、自社のデータを通じて間接的に競合の動向を把握する手がかりになります。
Googleアナリティクスの活用例
- ユーザーの流入経路や行動の傾向を把握し、競合との差を考察
- ランディングページごとのパフォーマンスを比較
サーチコンソールの活用例
- 表示回数が多いがクリック率が低いキーワードを特定 → 競合が上位を占めている可能性を検討
- 競合と争っている検索クエリでの順位変動を追跡
これらのツールは自社の改善点を見つけることを通じて、競合優位性を築く材料として活用できます。
競合分析を行う際の注意点
競合分析は、正しい視点とバランスを持って取り組むことで、分析の価値を最大限に引き出すことができます。ここでは、競合分析を行う際に特に注意したい3つのポイントをご紹介します。
情報収集に偏りがないか
競合分析では、正確な判断を下すために多角的かつ客観的な情報収集が必要です。特定のチャネルやツールのみに依存した分析をしてしまうと、視野が狭まり、全体像を見誤る可能性があります。
たとえばWebサイトやIR資料だけで判断するのではなく、SNS、口コミ、広告出稿状況、実際の顧客の声など、定量データと定性データをバランスよく組み合わせることが大切です。また、自社にとって都合の良い情報だけを拾ってしまう「確証バイアス」にも注意が必要です。
競合を過剰に意識しすぎない
競合の動向を把握することは重要ですが、競合の戦略を真似ることが目的になってしまっては本末転倒です。競合が展開しているキャンペーンや新商品のリリースに過剰反応し、自社の軸を見失ってしまうケースは少なくありません。
あくまでも競合分析は、自社のポジションや強みを再確認し、「どこで勝負するか」「何を差別化するか」を明確にするための手段です。他社の動向に振り回されず、自社のビジョンや方針に沿った意思決定を優先することが、継続的な競争優位性につながります。
分析結果の更新頻度に注意
競合環境は常に変化しています。新たな競合の出現、トレンドの移り変わり、テクノロジーの進化などにより、一度行った分析はすぐに陳腐化する可能性があります。そのため、競合分析は「一度やって終わり」ではなく、定期的に更新・見直す仕組みを整えることが重要です。
たとえば、四半期ごとに競合のWebサイトをチェックする、広告出稿状況をツールでモニタリングするなど、継続的な分析体制を整えることで、変化に強い組織づくりにもつながります。
まとめ
競合分析にはさまざまなフレームワークやツールがあり、正しい手順と視点を持つことで、マーケティングや商品開発、営業戦略など、あらゆる領域での意思決定に役立てることができます。また、直接競合だけでなく、間接競合や将来的に脅威となる潜在的競合までを含めて把握することで、より立体的で実践的な競争戦略を描くことが可能になります。
本記事の内容を参考に、自社の競合環境を改めて見直し、強みを活かした独自のポジションを築いてみてください。競合を知ることは、他社との争いではなく、自社の本質的な価値を再発見することでもあります。
競合分析の進め方やデータ収集・活用でお困りの際は、ぜひD2C Rまでお気軽にご相談ください。専門チームが、貴社の課題に合わせた最適な分析・支援をご提案いたします。
この記事が参考になった方は「いいね」やシェアをお願いします!
編集者
CANVAS編集部
編集者
CANVAS編集部
X(旧Twitter)はじめました。デジタルマーケティングに関する最新記事を公開日にご紹介しているので是非フォローしてください!@canvas_d2cr