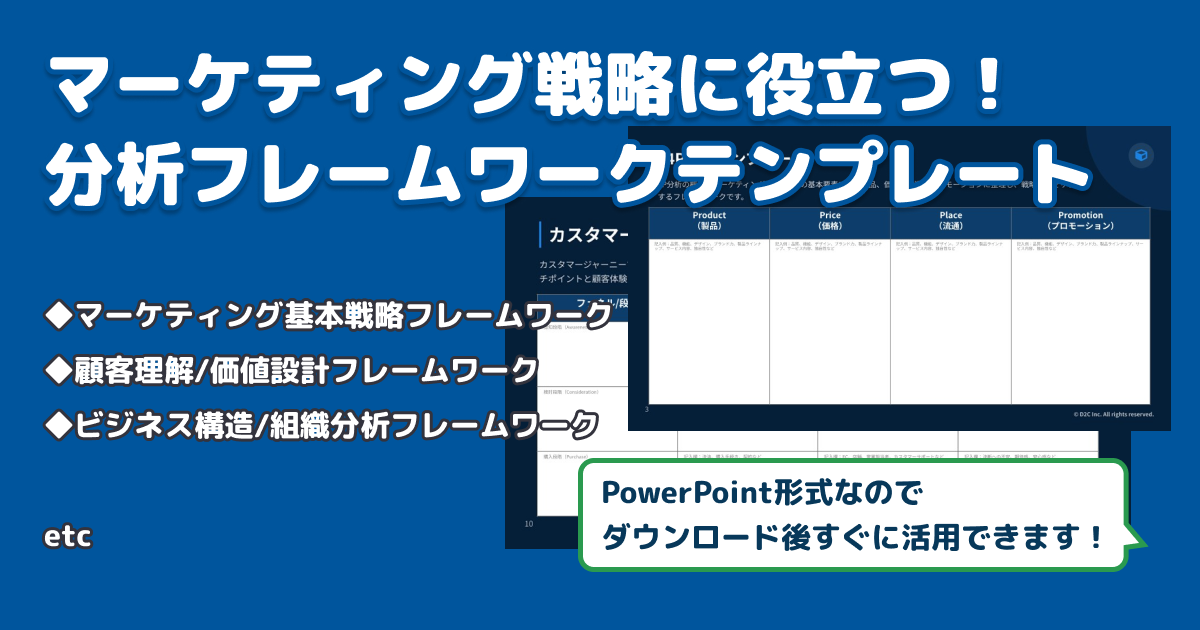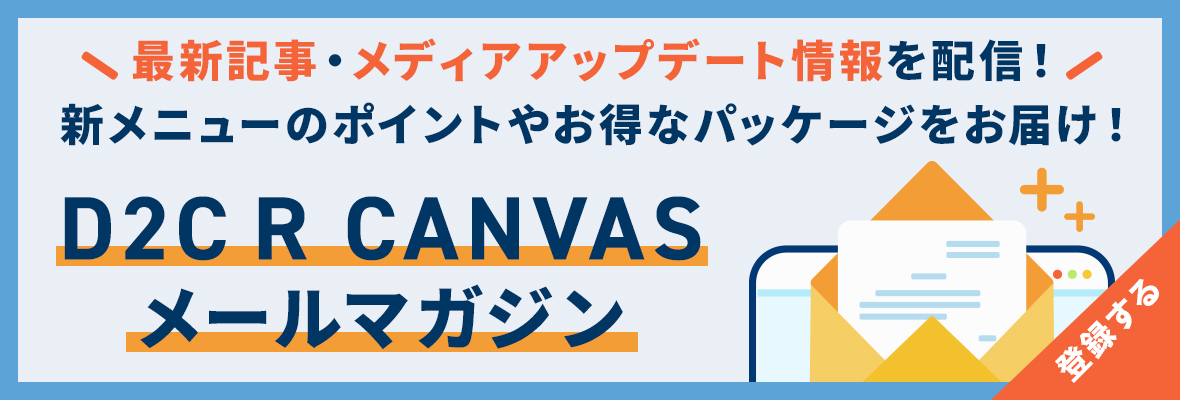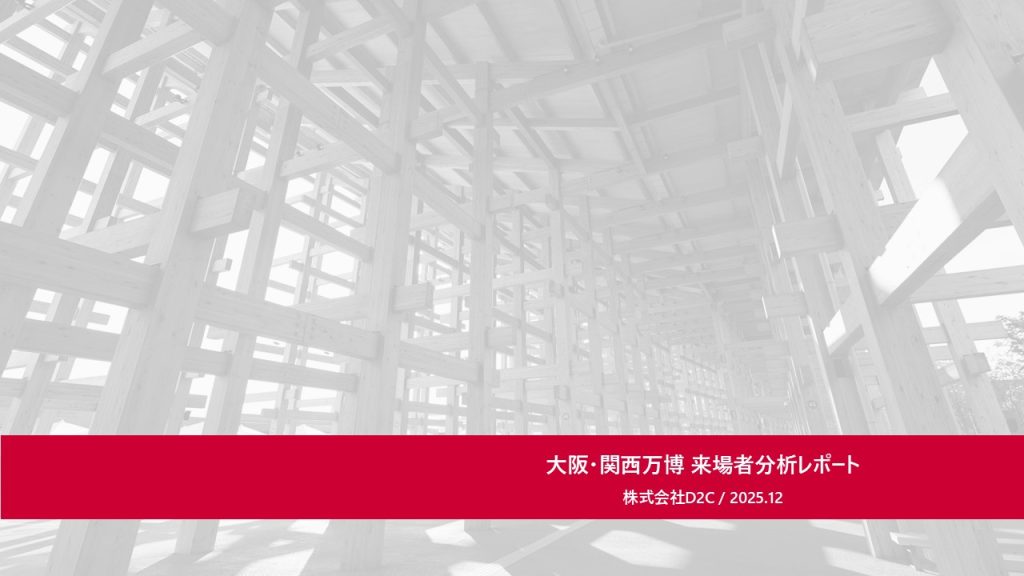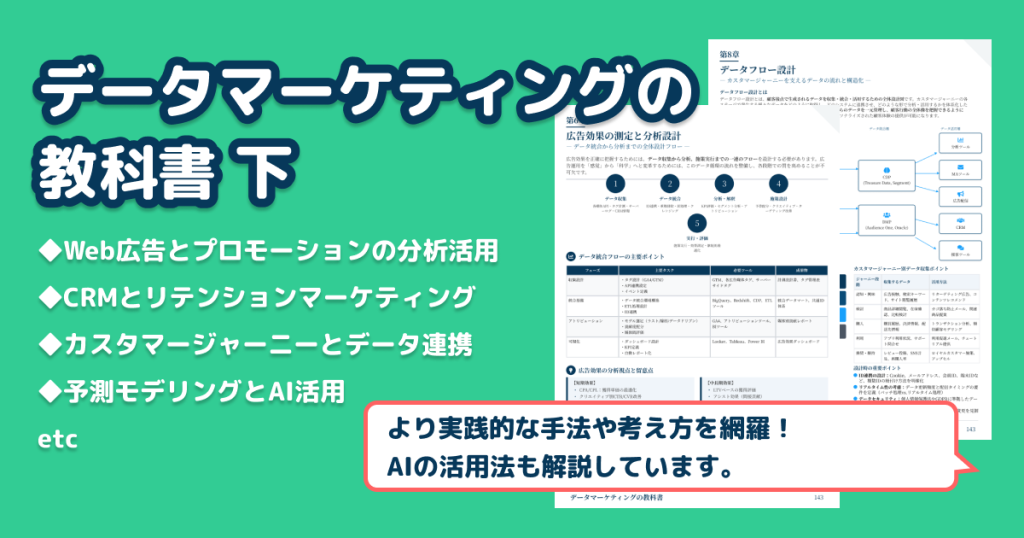競合他社とは?意味と競合の種類、競合分析・対策までわかりやすく解説

みなさん、こんにちは。
ビジネスを取り巻く環境が目まぐるしく変化する現代では、自社の立ち位置を把握し、競争に勝ち抜くための戦略を練ることが不可欠です。その中でも重要なキーワードとなるのが「競合他社」です。
今回は、「競合他社とは何か?」という基本的な定義から、具体的な種類、競合の見つけ方、そして競合との差別化や分析の方法までをわかりやすく解説していきます。
自社の強みを活かし、他社と差をつけるヒントを得たい方には特におすすめの内容です。
目次
競合他社とは?
ビジネスを進める上で、必ず意識しなければならない存在が「競合他社」です。自社の商品やサービスと同じ顧客層をターゲットにしている他社の存在は、売上やブランド認知に大きな影響を与えます。競合を正しく理解することで、自社の強みや課題がより明確になり、戦略的に差別化を図ることが可能になります。
ここでは、競合他社の基本的な定義、そして似たような概念である「ライバル」「代替品」との違いについて詳しく見ていきましょう。
競合他社の定義
競合他社とは、自社と同じ市場・顧客層に対して、類似または代替となる商品・サービスを提供している企業のことを指します。つまり、顧客の選択肢の中で「自社と競り合っている相手」が競合他社です。「同業他社」や「ベンチマーク企業」と呼ばれることもあります。
競合他社は、企業活動全般において影響を及ぼす存在であり、価格競争やマーケティング戦略、商品開発に至るまで、様々な側面で比較・分析の対象となります。
たとえば、食品の通販サイトを運営している場合、同様の商品を取り扱う他の通販サイトやスーパーマーケット、さらにはレストランも広義の競合となる場合があります。
「競合」と「ライバル」「代替品」の違い
「競合」という言葉は、「ライバル」や「代替品」と混同されやすい概念ですが、それぞれには明確な違いがあります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 競合 | 同じ市場・顧客層を狙い、 類似・代替の製品やサービスを提供する企業 |
| ライバル | 競技や成果を競い合う相手 (必ずしも同じ業界とは限らない) |
| 代替品 | 顧客にとって同じ目的・価値を満たす別の選択肢 (異なるカテゴリでも該当) |
たとえば、動画配信サービス「Netflix」にとって、「Amazon Prime Video」は直接の競合ですが、「映画館」や「ゲームアプリ」もユーザーの娯楽時間を奪う存在としては代替品にあたります。
また、同じ業界の中で毎年売上や実績を競い合っている企業同士は、ライバルと表現されることもありますが、マーケティング戦略上は「競合」として扱うべき存在です。
競合他社の種類
競合他社と一口に言っても、その性質や影響の度合いはさまざまです。市場の中で自社と競り合う企業は、大きく分けて「直接競合」「間接競合」「潜在的競合」の3つに分類できます。
直接競合(同じ商品・サービス)
直接競合とは、自社とほぼ同じ商品やサービスを、同じターゲット層に向けて提供している企業のことです。顧客にとっては、「A社の商品にするか、B社の商品にするか」をダイレクトに比較検討する対象になります。
具体例
- 自社がオンライン英会話サービスを提供している場合
⇒他のオンライン英会話企業 - 自社がランニングシューズを販売している場合
⇒同価格帯・同用途のスポーツブランド(ナイキ、アディダスなど)
このような競合は、市場シェアの獲得に直結するため、特に注意深く観察し、差別化を図る必要があります。
間接競合(代替品・異なるアプローチ)
間接競合とは、自社とは異なる商品やサービスであっても、顧客の「目的」や「ニーズ」を満たすという点で競合関係にある企業を指します。アプローチは異なっていても、顧客の選択肢として比較される存在です。
具体例
- 自社が学習塾を運営
⇒動画学習サービス、家庭教師、教育系YouTubeチャンネル - 自社がミネラルウォーターを販売
⇒スポーツドリンク、炭酸水、麦茶などの他の飲料
間接競合の存在に気づかないと、「競合がいない」と錯覚してしまうケースもあるため、顧客視点での広い視野が求められます。
潜在的競合(将来登場する可能性のある企業)
潜在的競合とは、現時点では直接的な競合関係にないものの、将来的に市場に参入し、自社のビジネスに影響を与える可能性のある企業や業界のことです。
具体例
- 異業種からの新規参入(例:電機メーカーがヘルスケア事業に参入)
- 海外企業の日本市場参入(例:中国の新興アプリが日本市場で展開)
- 新技術やビジネスモデルによる脅威(例:AIによる業務代替)
潜在的競合はすぐには可視化されにくいため、業界ニュースやトレンド分析、技術革新へのアンテナを張っておくことが重要です。
自社の競合を特定する方法
ビジネス戦略を立てるうえで、自社と競り合う「競合他社」を正確に把握することは非常に重要です。しかし、競合には直接的な相手だけでなく、間接的あるいは潜在的な相手も含まれるため、単に「同業者を調べる」だけでは不十分です。
市場・業界を俯瞰する
最初のステップは、自社が属する市場や業界を広い視点で俯瞰することです。自社の属する業界において、どのようなビジネスモデルや商品カテゴリが存在しているかを把握することで、競合となる可能性のある企業を絞り込みやすくなります。
俯瞰する時のポイント
- 業界マップや業界レポートを活用する
- 売上シェアや市場占有率が高い企業を調べる
- 同じ顧客層をターゲットにする周辺業種も視野に入れる
顧客視点での選択肢を分析する
次に重要なのが、顧客の立場で選択肢を考えることです。自社の商品やサービスを検討している顧客は、「どのような他の選択肢と比較しているのか?」という視点から分析を行うと、直接的な競合以外の存在にも気づくことができます。
分析のポイント
- 顧客アンケートや口コミを調査し、「他に検討したサービスは?」を聞く
- SNSやレビューサイトで顧客の比較対象となっている企業を調査する
- 購入前の検索キーワードや導線を分析する(例:Google検索、YouTube)
フレームワークを使って整理する(例:3C分析、ポジショニングマップ)
競合特定をより構造的に行うには、ビジネスフレームワークの活用が有効です。特に「3C分析」や「ポジショニングマップ」は、自社と競合との関係性や差別化ポイントを整理する際に役立ちます。
代表的なフレームワーク
- 3C分析(Customer・Competitor・Company)
→ 顧客・競合・自社の3視点で市場を把握し、差別化要素を明確にする。 - ポジショニングマップ
→ 「価格×品質」「機能×デザイン」など、軸を決めて競合との立ち位置を視覚化する。
▼分析方法についての記事はこちら
競合他社との違いを明確にするには?
競合他社を把握したあとは、自社との「違い」をいかに明確に伝えられるかが重要になります。どれだけ優れた商品・サービスを提供していても、顧客にとっての違いが伝わらなければ選ばれる理由にはなりません。
自社の強み・価値を洗い出す
差別化の第一歩は、自社が持つ独自の強みや価値を明確にすることです。ここで大切なのは、単に「特徴」を挙げるのではなく、「顧客にとっての価値」として捉える視点です。
強みを見つけるためのポイント
- 過去に選ばれた理由(営業・口コミ・アンケートから探る)
- 他社にない実績、ノウハウ、技術、対応力など
- 顧客が感じている満足ポイントやリピート理由
自社目線の「強み」ではなく、顧客目線での「価値」に翻訳することが大切です。
差別化ポイントの作り方(価格・品質・サービスなど)
自社の強みが明確になったら、それをもとに競合と差をつけるポイントを構築していきます。差別化の軸は業種によって異なりますが、以下のような代表的な切り口があります。
差別化の代表的な軸
- 価格:競合よりも安い、または高価格でもそれに見合う価値がある
- 品質:素材・製造・精度などで差をつける
- サービス:顧客対応、アフターサポート、スピード感
- デザイン:使いやすさ、ブランドイメージ、視認性
- 独自性:自社でしか提供できない技術や組み合わせ
特に重要なのは、「差別化=あらゆる特徴をアピールすること」ことではなく、特定のニーズに対して“尖らせる”こと。万人受けを狙うのではなく、「この人に選ばれたい」という明確な顧客像に向けて差別化するのが効果的です。
NTTドコモの分析サービスで競合分析
自社の強みを見つけ、他社と差別化を図るためには詳細な競合分析が必要となります。NTTドコモの分析サービスでは、貴社が展開されている商品やサービスの購買データと、他社の商品やサービスでの購買シーンの違いや顧客の違いを明らかにすることができます。その後、データを基に商品開発や差別化戦略、プロモーション戦略を検討することが可能です。
\ 1億超のデータから顧客を分析する /
まとめ
競合他社とは、自社と同じ市場・顧客層をターゲットに商品やサービスを提供している存在であり、ビジネス戦略において常に意識すべき相手です。直接競合だけでなく、間接競合や将来的に脅威となる潜在的競合までを含めて把握することで、より実践的なマーケティングが可能になります。
本記事でご紹介した内容を参考に、自社の競合環境を再確認し、強みを活かした戦略を考えてみてください。競合を知ることは、他社との争いではなく自社の価値を見つめ直すきっかけにもなります。分析でお困りの際にはD2C Rにお問い合わせください。
この記事が参考になった方は「いいね」やシェアをお願いします!
編集者
CANVAS編集部
編集者
CANVAS編集部
X(旧Twitter)はじめました。デジタルマーケティングに関する最新記事を公開日にご紹介しているので是非フォローしてください!@canvas_d2cr